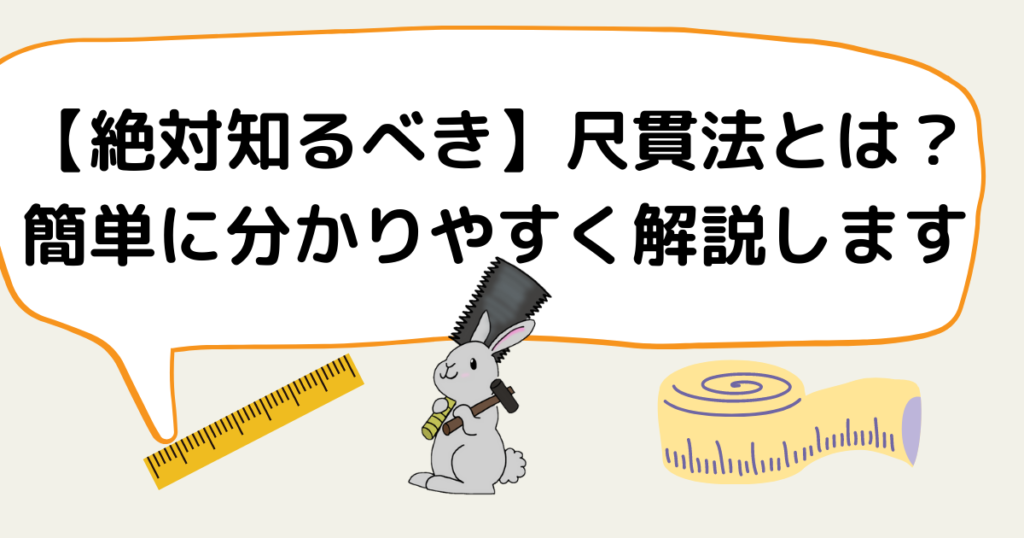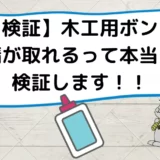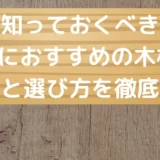当サイトにはプロモーションが含まれています
どうも、のこぎりうさぎです!
尺貫法(しゃっかんほう)という言葉を聞いたことがあるでしょうか?ネットで調べてもなんだか難しく書いてありますよね。
お爺さんやひいお爺さんが「大きさは三分(さんぶ)くらいだな」とか「六尺(ろくしゃく)もあるのか!」などを言っていたことはありませんか?
もっと身近な話でいうと、日本のお伽話「一寸法師」も尺貫法と関係あります。
「三分、六尺、一寸」はすべて尺貫法になります。
冒頭で分からなかった方も大丈夫です!記事を読み終えた後には、尺貫法を説明できるくらい分かりやすく解説していきます!
それではいきましょう!
尺貫法を聞いたことがない方
尺貫法は聞いた事があるけどよく知らない方
DIY初心者や大工を目指す方
尺貫法とは簡単に言うと「単位」です。より詳しく言うと「日本古来の計測法」です。
現在は「メートル法」が主流です。というより「メートル法の単位を使用しなければいけません」と法律で定められています。メートル法の単位は「m(メートル)」「Kg(キログラム)」などが使用されます。
ではなぜ現在に生きる僕が「尺貫法」なるものを知っているかと言うと、建設業界にはその計測法が根深く残っているからです!
大工さんは住宅を作るときに尺や分をよく使用します。と言っても本来の尺貫法とは少し異なります。
現在はメートル法で表わした尺貫法、いわば言い換えのような意味で使用されています。
少し分かりづらいと思うので、皆さんの生活に溶け込んだ尺貫法を例えに出してみます。
例えばお米は1日に何合炊きますか?二合でしょうか?それとも大家族で一升でしょうか?
実は合や升も尺貫法の単位です。容量を表す単位です。
容量の単位で有名なのは一斗缶で使用される「斗」も同じ容量を単位です。
他にも土地を購入する時などに一坪だったり、畑を所有している方は一反なんて表現したりすることもあります。
坪、反も尺貫法の単位です。これは面積を現す単位です。
まとめると尺貫法とは長さ、距離、面積、容量、あとは重さがを測る計測法の事を言います。
今回はDIYに関係のある長さ、距離を解説していきます。

ちなみに重さで有名な単位は匁(もんめ)や食パンなどで使われる一斤(いっきん)が有名だよ!
尺貫法はすごく奥が深いから全部は解説できないや。
とりあえず長さと距離だけ覚えてみよう!
ここからは尺貫法の単位の長さと距離をより詳しく解説していきます。
この長さと距離は住宅などのDIYをする時によく使用します。覚えると非常に便利なのでぜひ今後のDIYに活用してみてください。
長さ
尺貫法の中でも長さは非常に覚えやすい単位です。小さい単位から10倍したものが次の単位になり10倍を繰り返すことで大きい単位まで覚える事ができます。今回は単位をメートル法に直します。単位はすべて”mm”(ミリメートル)です。なぜなら建築の分野では”mm”で表すからです。
まず長さの小さい単位は厘(りん)です。メートル法で表すと0.303mmです。
次の単位は一分(いちぶ)です。メートル法で表すと3.03mmです。
次の単位は一寸(いっすん)です。メートル法で表すと30.3mmです。
次の単位は一尺(いっしゃく)です。メートル法で表すと303.03mmです。
次の単位は一丈(いちじょう)です。メートル法で表すと3030.3mmです。

丈は部屋の広さの一畳とは違う単位だよ
一畳は畳一枚分の広さだよ!
尺貫法とメートル法の単位の関係が分かりましたか?感覚的に覚えれば良いので、小数点以下は切り捨てで覚えても大丈夫です。
冒頭の例えに出した一寸法師は身長が所以の名前なので、身長は30.3mm(約3センチ)になりますね。小さいと捉えるか大きいととらえるかはあなた次第です。

ちなみに厘より小さい単位も存在するよ!
毛(もう)といって一毛は0.03mmだけど、小さすぎる単位なので覚えなくても大丈夫!
単位別に表を作成したので参考にしてください。
| 尺貫法単位 | 小さい単位 | メートル換算 |
| 1厘 | 0.303mm | |
| 1分 | 10厘 | 3.03mm |
| 1寸 | 10分 | 30.3mm |
| 1尺 | 10寸 | 303mm |
| 1丈 | 10尺 | 3030mm |
距離
次に距離を測る単位を解説していきます。
「長さと何が違うんだ」と思うかもしれません。明確な定義はないですが、区別しておくことで覚えやすくなります。
僕は区別しないで覚えた為、覚えるのに非常に時間がかかりました。仮に定義付けるとすれば「手に持って測れるものが長さ」「手に持って測れないものが距離」としましょう。
ただし距離といってもDIYに重要な単位はたった一つだけです。
それは間(けん)これから何種類か単位が出てきますが、DIYで使用するなら間だけ覚えれば大丈夫です!
それでは解説していきます!
まず間の前にもう一つ、距離で重要な単位が尺です。長さでも出てきた尺です。一尺303mmですね。
次の単位は間(けん)です。超重要なので必ず覚えて欲しい単位です。一間の距離は1820mmです。六尺が一間になります。正確には一間(六尺)は1818.18mmですが、なぜそうなのかは重要な理由として併せて後述の「住宅との関係」で解説します。
次の単位からは住宅ではほぼ使用しません。念の為知識として覚えておくと役立つかもしれません。
次の単位は一町(いっちょう)です。間でいうと60間です。距離は109.09メートルです。
次の単位は一里(いちり)です。町で言うと36町です。距離は3.93キロメートルです。里の単位は海などで使用されています。
こちらも表を作成したので参考にしてください。
| 尺貫法単位 | 小さい単位 | メートル換算 |
| 一尺 | 303mm | |
| 一間 | 6尺 | 1820mm |
| 一町 | 60間 | 109.09メートル |
| 一里 | 36町 | 3.93キロメートル |
ここからは尺貫法と住宅の関係性を解説していきます。
住宅との関係が分かるとより理解しやすくなると思いますのでぜひ参考にしてください。
長さの単位の関係
長さの単位との関係は主に分、寸、尺が関係します。ではどこに関係しているのか解説していきます。
まずはホームセンターなどで売られている合板や石膏ボードのサイズは3尺×6尺(サブロク板)で販売されています。
ただし実際は正確な寸法よりも、少し大きめの910×1820のサイズになっています。
900×1800でもサブロクということもあるみたいです。
現代では正確には尺貫法は使用できないためメートル法に換算されています。なので大まかな寸法で使用されています。
寸と分はおもに材料の大きさに関係してます。木材には定尺寸法という規定の大きさがあります。
それを測るのが寸と分です。例えば大工さんは材料を「いんごいっぱち」「いっさんいんご」と材料を呼びます。
職人さん以外はほとんど聞いた事がないと思いますのでしっかり解説していきます。
まず「いんごいっぱち」とは一寸五分×一寸八分(45×55)のことです。数字だけを読んだ略語です。
同じように「いっさんいんご」一寸三分×一寸五分(39×45)になります。
まだ関係あるものはありますが、この辺りを覚えておくと便利です。
距離の単位の関係
距離の単位との関係はほとんど「間」です。ちなみに一間は六尺でした。ただし1820mmでしたね。これは先ほど長さでも説明した合板の大きさと同じ理由です。
それと間が非常に重要と解説しました。なぜ間が重要かというと、住宅の柱が入っている距離だからです!
ただし正確にいうと少し違います。一間ごとに柱を入れなければ柱と柱の間に入れる梁を大きくしなければいけないと、建築基準法で定められているからです。ということは一間間隔で入れれば、梁を大きくしなくて済む訳です。
大きくしなくて済む一番の理由は「大きくすると金額が上がるから」です!とは言っても住居を作る以上、部屋の中の間隔は1間以上あります。なので主に壁の中の話だと考えて頂ければ分かりやすいかと思います。
ではなぜ梁を大きくしなければいけないのかは、建築基準法の構造力学という難しい話になるのでそういうものだと思って頂ければ大丈夫です。
振り返りますが一間とは1820mmで六尺です。他にも半間といって一間の半分の距離910mmもよく使用されます。半間は3尺です。半間とは通常柱を入れる距離です。
なんだか混乱してきましたね。一旦整理します。
- 「半間」は開口部などが無い場合、柱を入れる距離です。なので開口部のない壁の中には半間ごとに柱が入っています。
- 「一間」は開口部などで半間ごとに柱を入れられない場合に、梁を大きくしなくても良い距離です。なので一間以上の開口部を設置すると梁が大きくなります。
併せて覚えてほしいのが、半間の更に半分の455mmです。長さは一尺五寸ですね。これは間柱を入れる間隔です。
間柱とは、構造には関係しない柱です。壁の下地のための柱だと覚えると分かりやすいです。
この間を覚えてくと、DIYで壁にビスを留める位置が分かるので便利です。
尺貫法は日本古来の計測法です。ただし現在はメートル法に置き換わり、正確な尺貫法は使用できない決まりになっています。
それでも尺貫法は日本の文化と結びつき、現在でもその名残が残っています。
特に建設業界は名残が強く、現在でも尺貫法の単位を使用する場合があります。
建築の世界では、尺や間はよく耳にする単語です。ただしそれが尺貫法の単位でどのくらいの長さ、距離なのかを理解しなければ、正確に相手に伝えることも理解する事も出来ません。なのでこの記事を読み、尺貫法がどの様な物なのか少しでも伝われば嬉しいです!
今回は「尺貫法とは何なのか」を記事にしました!
今回の記事で尺貫法が理解できた、面白かったと思って頂けたら嬉しいです!
最後まで読んでいただきありがとうございました!
 のこぎりうさぎ工房
のこぎりうさぎ工房